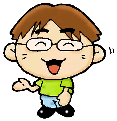なあ……たのむ。
助けて……許してくれ……!
目の前の男はそう言って命乞いをした。
助ける? 許すって……?
なぜ助けなくてはならないのか。
この男はいったいなにを許せというのだろう。
わたしは確かに狂人だが、わたしを壊したのはこの男ではないのか。
自分で撒いたタネだというのに、今さらわたしに何を許し、誰を助けろというのか……。
*
わたしは何もかもが破綻した掃き溜めのような家に生まれた。それは半分沈みかけたボロ船にちがいなかった。
いちばん古いわたしの記憶は母の手だ──
もちろんわたしを抱きしめるための手ではない。
わたしの頬をつねり、尻を叩き、全身を殴るための道具だった。
記憶の中にある母の目はいつでも真っ黒で無表情だ。
あとになって思えば、それは人間の目ではなかった。
いつか学校の図書室で見た図鑑に載っていた、あのサメの目と同じだった。
サメの目でわたしを折檻する母。
それがわたしに思い出せるいちばん最初の記憶だ。
物心つくまでずっと同じ記憶しかない。
助けてくれる人なんていなかった──
父は折檻されるわたしを見ていつも笑っていた。
そしてわたしが十一になったころ、今度は父に犯された。
母は犯される私の姿を見ながら行為にふけった。
まだ初潮さえなく、自慰すら知らなかったわたしの体は、それでも繰り返し犯されるうちに感じる体になっていった。
それが悔しくて泣くと、父はさらに喜んでわたしを犯した。
わたしは毎日のように、いつだって父がしたいときに犯された。
母はわたしの悲鳴を聞きつけると必ずやって来て、特等席からわたしの泣き叫ぶ姿を楽しんだ。
自分の股ぐらに指を這わせながら。
人間はここまで残酷になれるのか……そんなにも人の心は壊れてしまえるものなのか。
その驚愕と疑問を再現してみせる悪夢のような日々だった。
唯一の逃げ場所は学校だったが、単に両親の目が届かないという安堵があるだけだった。
自身の淫らな境遇に負い目を感じ、いつも何かに脅えているわたしに友達ができるはずもなく、救いを求めることさえできなかった。
そうやって野良犬のようにびくついて暮らし、犯されならがらわたしは生きた。
やがて犯される私を鑑賞するのに飽きたのか、母は父の行為に荷担するようになった。
父がわたしの中を突き始めると、母はなにをやっていてもそれを中断し、嬉々として駆けつけた。
そしてわたしのお尻に巨大な注射器を突き刺すのだ。
下腹に父の熱いものを咥え込んだまま、後ろには何リットルものグリセリンを流し込まれるのだ。
わたしのお腹は妊婦のように膨れあがった。
まるで腸や胃が内部で暴れているような感覚だった。
お腹が張り裂けないのが不思議なほどだった。
その新しい遊びは両親の定番となり、わたしは日ごと前後の穴を陵辱され、苦痛にあえいだ。
三回に一度は失神し、このまま死ぬのだと何度も思った。
それでも元来から淫乱の素質があったらしく、わたしのお尻はすぐに犯される快楽を覚えた。
来る日も来る日も前後の穴を同時に責められ、犯されながら、わたしは気持ちよくて悔しくて泣きながら何度もイッた。
そんな生活が一年も続くと、いつしかわたしは立派な変態になっていた。
相変わらず父も母も憎かったが、体だけは快楽に反応した。
もはやわたしの小さな割れ目はべつの生き物みたいに反応し、いつだって父の太いモノが欲しくてだらだらと涎をたらした。
お尻の穴は母の浣腸が恋しくてヒクヒクと脈打った。
そのことがとても嫌で、同時に快感だった──。
これほど完璧な拷問がほかにあるだろうか?
この世で最も憎んでいる相手に犯され、恥辱され──だが気持ちとは裏腹に体はそれに応じ、快楽に身をよじるのだ。
両親もそのことを知っていた。だから奴隷であるはずのわたしを軟禁することもせず、足枷さえ必要なかった。
彼らの元でしか味わうことのできない快楽が、わたしを縛る鎖の代わりだった。
何度も逃げようと思った。でもダメだった……。
せいぜい一日か二日、そう遠くない周辺をさ迷い歩くのが関の山だった。
行くあてもなく街をふらつき、人気のない夜の公園でベンチに横たわる。
何もしないでいると、わたしのイヤらしい体はすぐにでもうずき出す。
そっと割れ目に手をやると“おもらし”したみたいに濡れていた。
お尻の穴もパックリと口を開け、熱を持っているのがわかる……。
わたしはたまらずに身悶えすると、何かのスイッチが入ったように自分の指を前後の穴に突っ込んだ。
通行人の存在を気にする意識など、はなから消し飛んでしまっていた。
それほどに快楽に飢えていたのだ。
前と後ろに指を入れて激しく動かす。
ひっそりとした夜の公園にわたしの淫らな声が響きわたる。
だが到底そんなものでは満足できなかった。それどころか寝た子を起こすような行為だ。
もっと強く……もっと激しく!
わたしの体はそう要求していた。
肉体だけの問題ではない。
精神的な部分でも、憎い憎いあのふたりから受ける責めでなくては、本当の快感など得られなかった。
身も心も、完璧な奴隷として調教されてしまったのだ。
ああ……やっぱりダメだ。
……あの太く脈打つ肉の棒で掻き回されたい。
激しく突かれたい。
お尻の穴を犯してもらいたい……!
勢いにまかせて家から飛び出す気力はあっても、そこから先の思考力などないに等しかった。
もちろん死ぬ勇気さえない。
火照った体を自分ひとりではどうすることもできずに、結局わたしは追い詰められるようにして家へと駆け戻るのだ。
両親はそのことを熟知していた。
だからわたしが家出をしても、決して探そうとはしなかった。
わたしが必ず舞い戻ってくることがわかっていたから。
そして家出をしたあとには、さらに激しい責めがわたしを待っていた。
好き放題に蹴られ、殴られたあと、わたしはゴミみたいに引きずられて地下室へと運ばれた。
わたしは引きずられながら、あちこちに受けた痛みを反芻し、その余韻にうっとりしている自分を恥じ、かれらを呪いながら自身の股ぐらを弄った……。
まるで中世の拷問部屋のような地下室にわたしを放り込むと、父はわたしの体を縄で縛りあげた。
解体を待つ肉のように縛られ、天井から吊るされたわたしは全身に父のムチを受けた。
ムチの音が響くたび、わたしの体に針を刺すような痛みが走り、それが痺れをともなって薄れるときには快感となってうずいた。
わたしは泣いて声をあげた。
快感と憎悪と自身への嫌悪が詰まった叫びだった。
その合間にも父はわたしの口内で射精し、何度も子宮内に白濁を注ぎ込んだ。
そうやって父がわたしの割れ目に突っ込んでいる間は、母はわたしのお尻の穴に液体を注入し、道具を刺し込んで激しく突いた。
ふたりは吊るされたわたしの周りをぐるぐると回り、手を変え品を変えてありとあらゆる折檻をしては罵り、なぶり、叩き、突きまくった。
わたしは泣き、叫び、失禁しては排泄した。
涙と涎をたらしながら憎悪と快感の中で何度も絶頂を迎えては気絶し、失神しては絶頂した。
狂おしいほどの痛みと快感のなかで、わたしはあらためてかれらに対する憎悪を知り、自身への嫌悪を知った。
そして何よりも快楽に溺れている自分を知った……。
*
そんな酷い家庭でも経済面で困ることはなかった。
いや、どちらかと言えばお金持ちだった。
かれらが裕福だから倒錯した世界に走ったのか、それとも気狂いだからお金持ちになれたのかはわからないが。
それが理由なのか、わたしはこの家の奴隷ではあったが、外に対しては恵まれた幸せな子として陳列された。
きっと両親の仕事に関係していたのだろう。
いわゆる世間体や見栄といったものだ。
だからうちに来客があると、わたしは普段よりもさらに高価な服を着せられ、お人形のように扱われた。
もちろん体中の傷と縄の跡は豪華な衣装で隠れていた。
そして狡猾な父母は決してわたしの顔を傷つけなかった。
わたしはシルクよりも上等なぴかぴかの真っ白い肌と、端正で愛くるしいドールの顔を生まれ持っていた。
我が家に招かれた上流の客たちは、わたしの美しさに目を丸くし、褒め称え、心を奪われて帰ってゆくのが常だった。
だがやがて、うちにくる客の大半はわたしの上を通り過ぎるようになっていった。
最初にそれを思いついたのは母だった。
すでにあらゆる責めをやり尽くした両親はいつもイラついていた。
かれらのように病的なまでに趣向を探求する者が必ずたどりつく、マンネリズムという袋小路にはまり込んでいたのだ。
そんな日々のなか、母はふいにそれを思いつき、父に提案したのだ。
父はさっそく信頼できる交友関係をリスト化すると、秘密のサロンを立ち上げた。
そうしてほうぼうに案内状を送りつけると、その日のうちにたくさんの人たちが我が家に集った。
わたしは来客者の注目する中で裸に剥かれ、股を広げた格好で縛られ、宙に吊るされた。
そして前に道具を刺されたまま後ろからは液を注入された。
そのあられもない恥かしい姿態をギラギラしたたくさんの目で視姦された。
わたしは恥かしくてぼろぼろと泣いた。
だが体に染みついてしまった淫乱は、たちまちわたしの性器と肛門から反応を引き出した。
わたしの小さい割れ目は太い道具を咥えたままだらだらと愛液を流し、お尻の穴は性器みたいにヒクヒク動いて大量の液を飲み続けた。
見も知らぬ大勢の大人たちに恥辱されるその行為は、両親から初めて辱めを受けたときの気持ちをわたしのなかに甦らせた。
すでに快楽を求めてやまないわたしの体は、その新鮮な刺激に濡れ、息を吹き返した羞恥心がさらなる快感をもたらした。
あまりの官能に触れたわたしは、道具を咥えた割れ目から放尿し、体を痙攣させて限界に達した。
その後もわたしは何度となくイかされ、失禁し、注入されては排泄した。
大人たちの貪るような視姦の中で垂れ流す行為は、もはや至福でさえあった。
そして、完全に自我を失い、快楽を求めるダッチ・ワイフと化したわたしを、大人たちは犯した。
つるつるした赤ん坊みたいなわたしの割れ目に、太い肉棒が容赦なくねじ込まれた。
お尻の穴には別の大人のものが挿入され、待ちきれない者はわたしの口にそそり立ったモノを入れた。
穴という穴を全て塞がれ、同時に突かれ、わたしは犯された。
その羞恥と苦痛と快感のくり返しは、まさにこの世のものとは思えない極上のゆりかごだった。
下手をするとわたしは快楽で死んでいたかもしれない。
イってもイっても責めは終らないのだ。
大人たちはまるでアトラクションの順番を待つ子供みたいに列をなし、次々とわたしの前後に熱いものを刺し込んでは吐き出して行った。
もちろんその中には父もいた。
母はわたしの前後のどちらかが空くとその穴を責めながら、あぶれた男を捕まえては求めていた。
だがもうそんなことはどうでもよかった。
わたしは気狂いのように泣きながら悲鳴とも笑いともつかない叫びをあげて感じ、腰を振ってよがり、大人たちの太いモノを受けとめた。
いったい何人の精液を飲み干し、どれほどの白濁がわたしの子宮とアナルに注ぎ込まれただろう。
その狂乱の宴は夜通し続き、わたしは陽が昇るまで陵辱され、犯され続けた──。
*
きっとわたしは、そのときすでに壊れていたのだ。
そんな狂った営みがしばらく続き、わたしはもう家出さえしなくなっていた。
父母に対する憎悪が消えることはなかったが、快楽への欲求はそれ以上にわたしを翻弄し、骨抜きにしていた。
わたしは十三の歳を迎え、より官能の味を知り、急速に発育し始めた体は責めに対するバリエーションをかれらに提供した。
だがそれも今日で終る。
わたしは足元に転がった肉塊──かつて母だったものに向かって、もういちど引き金を絞った。
短い破裂音が響き、すでに肉と化していた女の頭が半分になった。
飛び散った血と肉片が床に鮮やかな模様を作る。
その光景を見て男の体がビクン、と跳ねた。
元わたしの父だった男だ──。
な、なあ……許して……助けてくれ!
男は命乞いをした。
わたしは無言で銃口を男に向けた。
わたしは狂っている。
そう。この男と同じだ。
そのまま引き金を引いた。
*
わたしは家中のお金をかき集めると、手荷物だけを持って外に出た。
これから何処へ行けばいいのか。
何を思い、何を感じ、いったい何を糧に生きてゆけばいいのか……。
わたしに与えられなかった良心の隙間──満たされなかった愛情……誰かを大切に想う気持ち……自身をいたわる感情……あらゆる観念と道徳……それを制御する理性。
わたしにとっては全てが理屈だけの公式であり、経験を伴わない絵空事だ。
そんな空虚な心をさらしてどう生きればいいのか──また生きてゆけるのだろうか。
ひとつはっきりとしているのは、わたしの心の裂け目が埋まることは決してないだろう、ということだ。
この体に染みついた性癖は一生わたしについてまわり、もう普通の生活に戻ることなどありはしないのだろう。
たとえかれらを殺さなかったとしても。
ともかくひとつのことが終り、これから始まるのだ。
それはわたしにとっての苦難かもしれないが、これからのことをゆっくり考えようと思う。狂ったわたしなりに。
──完。
|